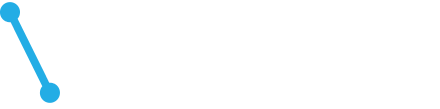全般
皆さんのまわりにある家電や工業製品が作られるときのことを考えてみてください。こういった「ものづくり」に「理」の力が重要であることは論を俟ちませんが、理系の力だけで工業製品が作れるわけではありません。たとえば、スマートフォンが魅力的な製品として世の中に送られるためには、優れた技術(基板や回路やプログラム)を作るだけではなく、かっこいい画面や筐体のデザイン、使いやすく魅力的なユーザインタフェース、といったデザインの要素が絡んできます。これには「芸」の力が必要です。さらに、生まれた製品を世の中に送り出すためには、ものづくりを行うための資金調達はもちろん、会社組織の運営や、流通・販売といった面でもサポートが必要です。ここに「文」の力が必要となります。
INIADの「文芸理融合」では、文芸理それぞれの人材が、コンピュータとコミュニケーションの能力を基本として持ち、それぞれの専門を生かして協力・連携し、これからの産業を支えていけるようにすることを目指しています。カリキュラムにおける1年次のコンピュータ・コミュニケーションの必修化、2年次以降のチーム実習もそのような考えに基づくもので、他の情報系の大学や学部ではみられない、今の社会に求められるカリキュラムとなっています。
入試関連
資格としては、情報分野であれば情報処理技術者試験への合格、ビジネス分野であれば簿記検定試験への合格などが想定されます。コンテストとしては、情報分野であればプログラミングコンテスト、デザイン分野であればデザイン関連のコンクールなどが想定されます。このような資格やコンテストに限らず、例えばボランティア活動等の学内外での活動の実績でも構いません。ただし、自分の実績をプレゼンテーションにおいてアピールできることが求められます。特定の実績があれば合格になるという入試ではないので、ご注意下さい。
一般入試の詳細は東洋大学入試情報サイトを見て頂ければと思いますが、例えば一般入試3教科型(理系)であれば、英語、数学、理科の組み合わせで受験することができます。自分にあった入試を受験してください。
- 外部試験を受験していなくても出願できるが、外部試験の得点結果が利用が可能なもの・・・一般入試 前期
- 外部試験の得点結果が出願資格として必要なもの・・・一般入試 総合問題型
カリキュラム
INIADの1年次カリキュラムは、プログラミングを基礎から丁寧に学ぶことからはじめ、様々な応用分野にプログラミングを活用できるようにするために必要な能力を獲得できるように設計されています。まじめに取り組めば、1年後にはプログラムを書いていろいろな課題を解決できるようになっているはずです。
INIADの1年次カリキュラムでは「反転型学習」とよばれる仕組みにより、全員が同時に同じ授業を同じペースで聴講するというスタイルではなく、MOOCs(オンライン学習システム)を用いて自分のペースで理解を進めることができます。オプションとして発展的な内容も用意されており、プログラミングが得意な皆さんでも十分にやりがいをもって取り組める授業を用意しています。
INIADでは4つの分野(ビジネス・シビルシステム・エンジニアリング・デザイン)について専門科目が用意されており、それぞれの立場からコンピュータやプログラミングを実社会に応用するための方法を学ぶことができます。INIADの学生は1年の間に一つ専門分野を選び、選んだ専門分野のいくつかの講義や演習を確実に履修し、自分の専門を確立するための仕組みを用意しています。この仕組みが「コース」です。
一方で、自分の選択したコースの専門科目だけでなく、自分の興味に合わせて色々な専門分野の科目も自由に組み合わせて受講することができ、むしろそのようなコース横断的な履修方法を推奨しています。また卒業研究でも、自分の選択したコース以外の研究室を選択することもできます。
一般的な学科においては、学科ごとにカリキュラムが用意されており、それぞれにおいて必修科目や受講できる科目が決まっています。INIADは単一の学科(情報連携学科)からなっており、どのコースを選んだとしても様々な専門分野の科目を組み合わせて受けることができます。
なお、どのコースに進んだ場合でも、他のコースの授業を受けることはできるので、その点については安心してください。
※ 本ページの記述は計画段階のものであり、変更となる場合があります。